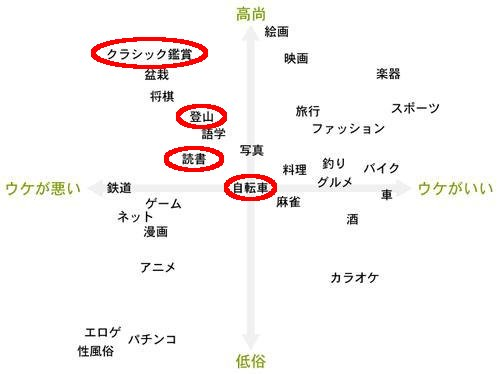ふとフィクションが読みたくなったので、図書館に行くことにした。生まれ育った町に住んでいるので、この図書館はかれこれ20年は間利用している。小さい図書館で、レイアウトなんかは昔から全くと言っていいほど変わっていない。変わったことと言えば、ビデオテープがDVDに変わったことと、自動チェックアウトの機械が新しくなったくらいだ。ちなみにWifiが無料で使えて冷房も効いているのでなかなか快適でもある。カタログはあまり大きくないがメジャーどころは大抵揃っている。
駐車場がかなり混んでいたので、車から最寄りの入り口が裏口になった。この裏口、最低でも15年は通ってないのでそもそもまだ存在しているのかも疑問だった。春草も瑞々しさが無くなって来たなと植木群を見ながら感じ、裏口にさしかかった。裏口は幸運にもまだ健在で、その脇では近所の高校生らしき女の子が紺のTシャツとデニムのショートパンツ姿で携帯電話で相手を捲し立てていた。そんな彼女を片目に僕は図書館に足を踏み入れた。半年ぶりだ。
児童書と一般書は別の区画にあるので、まず児童書のエリアで"The Giver"の続編に当たる"Gathering Blue"と"Messenger"を見つけ、SF的な物も読もうと思い一般書のSFエリアでKurt Vonnegutの本を2冊適当に選んだ。Vonnegutの有名な作品は既に読破していたので、あまり深く考えずに裏表紙の売り文句を参考にした。なぜVonnegutかというと、彼のネジの飛んだスタイルが口直しにはちょうどいいからだ。ちなみにLois Lowry著の三部作は児童書でありながらも成人でも楽しめる稀な本だ。1冊目を初めて読んだのは17年前だが、アラサーの僕が今年読みかえしても面白いと感じた。
と、そこで最近聞いている"The Incomparable"という超ギークポッドキャストで話題になっていたCormac McCarthyの新作、"The Road"のことを思い出し、フィクションの"M"の棚へと向かった。Cormac McCarthyは純文学作家で、"All the Pretty Horses"というカウボーイを描いた三部作が有名らしいのだいが、新作は核の冬が訪れつつある、すべての生き物が死んでいく中で父と子が ー こうして書くと娘ではなく息子がイメージされるのは何故だろうか ー 絶望しかない中で生きていくという「正にSF!」という内容らしい。Mの棚の後ろ側から"MC"を探して進んでいく。するとふと村上春樹のことを思い出し、彼の英語版の本があるか気になった。探してみるかと思い立つと、2分としない内に見つかった。
1Q84がでかでかと自己主張していた。厚さ3センチ、高さ20センチ以上。1Q84は日本では何冊かに分かれて出版されていた記憶があるのだが、英語版では1冊にまとめたのではないかと思えるくらい巨大だった。見かけが同一のものが4冊もならんでいた。前々から村上春樹の本を原文と訳文とで読み比べたいと思っていたので、去年読んだ「国境の南、太陽の西」と「ノルウェイの森」を借りることにした。
肝心のCormac McCarthyはというと、残念ながら"The Road"はなかったので"All the Pretty Horses"を代わりに借りることにした。いま考えると"The Road"はSFなので、フィクションのエリアではなくSFのエリアにあったのかもしれない。今度行くときは調べておこう。
十日後の今、僕の手元にはまだこれらのフィクションが5冊ある。Lowryの2冊は読み終わっているので、「国境の南、太陽の西」を次に読むことにした。村上春樹は原文自体が文体・スタイル共に英文作家のそれに似ているらしいので、英翻訳は比較的原文に忠実なのではないかと期待している。僕自身、文体が村上春樹に似ていると言われたりするが、それは僕の文章構成や言い回しが英語ベースなことが少なからず起因してるだろう。まあもちろん、共通の名字が連想の元なのは間違いないだろう。
さあ、と腰を据えて読み始めた僕は1文目からいきなりこの英訳に違和感をおぼえてしまう。"My birthday's the fourth of January, 1951" と訳されているが、原文のあの澄ました様なかっこつけた様な主人公の1人称は"My birthday is" を "My birthday's" に省略したりはしないと思う。8ページ目には主人公が "Woah" なんてカジュアルな表現を使っている。どう考えても場違いだ。原文のあの村上春樹独特の半歩引いた、鼻にかけたトーンや言い回しが損なわれていると思う。
8ページしか読んでないのにこうも酷評するのは自分でも少しばかり気が引けるのだが、「作風」というのは読んで字のごとく、作品全体を通して一貫しているものだ。2、3ページも読めば感触として伝わってくる。僕はそれでも最後まで読むつもりなのだが、こんな序盤でがっかりさせられたのは残念だ。ストーリーを既に知っていて、「表現」を読む事が唯一の目的であることも災いしているのだろう。
ネットで何かをこういう風に叩く場合、デフォの反論は「じゃあお前がやれよ」や「じゃあお前に出来るのかよ」だが、少なくとも後者は肯定できる。語彙は少ないし文体はストレート、そして英語でのトーンのコントロールは僕が書き手として得意とするものだ。前者は流石に不毛なので遠慮したい。しかしやってみたいものの一つではある。
「お前今ニートだろ?今やらないでいつやるの?」
「今でしょ!」 (ゴメンナサイユルシテクダサイ)