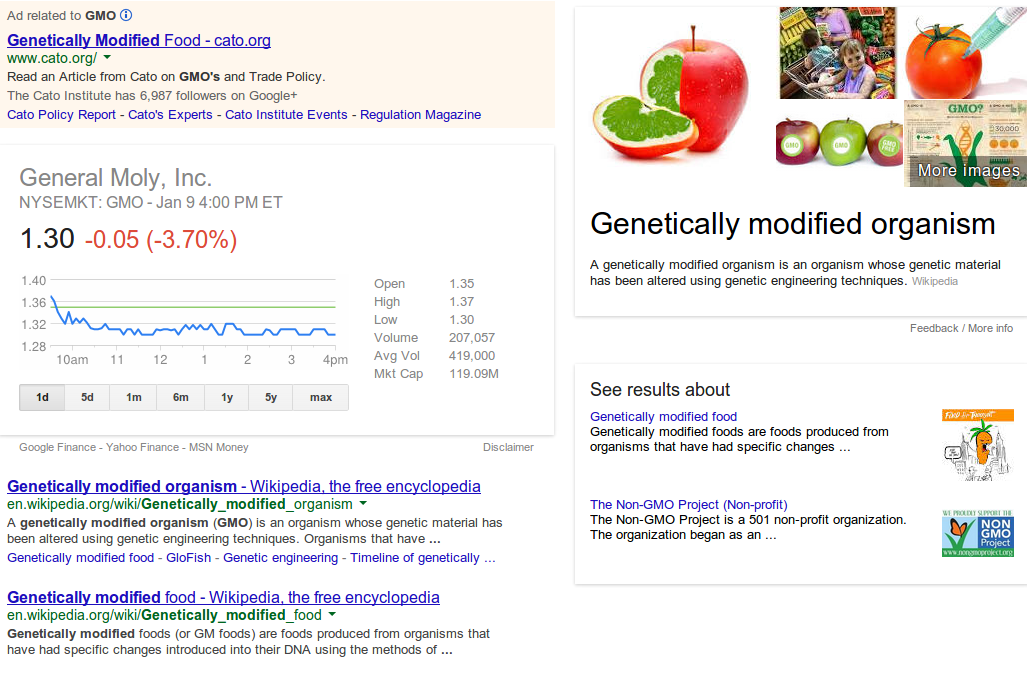Fluentdのドキュメント担当の@hkmurakamiです。主にエンジニアコミッタの面々から上がって来た、ほかほかのドキュメントを「えいや!」と編集するのを担当しています。
これはFluentd Advent Calendar。。。とは関係無いですが、似たような文脈で書こうと思います。
進捗どうですか?
2013年には新たに40のドキュメントが書かれ、新たに381のコミットがされました。1日に約1コミットですね。
2012年、末のスナップショット:57 docs、162 commits
2013年、末のスナップショット:97 docs、543 commits
日本語ドキュメント
@repeatedlyもAdvent Calendarで書いていますが、2013年はドキュメントの日本語版がスタートしました。@mazgiさんが4番バッターですが、最近は他の有志によるPull Requestも見るようになり、内心「おおっ!」と感無量です。
今後
これまた@repeatedlyの二番煎じですが、日本のFluentdコミュニティの方々が実践してくれたユースケースを英訳していきたいですね。
この間、@kiyototamuraに、「おらおら、英訳しろや!」と脅されて、@kazeburoさんのGrowthforecastのドキュメントを英訳させてもらったので、Fluentd+Growthforecast関連のユースケースが近々英訳されるのではないかと思ってます[1]。
ユーザーにバリューを提示してなんぼだと思うので、そういう面でユースケースは欠かせないんじゃないかと思ってます。
個人的所感
To be エンジニア、or not to be エンジニア
僕はエンジニアでは無いので、書いてるドキュメントの中身が良くわからなくてつらぽよ。。。みたいな事が結構あります。ここ最近では、更に貢献するためにはコアはまあ無理として、プラグインのソースくらいは読んで、それに自分でFluentdを運用してみないといけないなと感じてます。やはり中身がわかってないと、外堀を固める仕事のクオリティにも限界があることを実感しています。
@kzk_mover
Fluentdドキュメントのコミット行数は、@kzk_moverが今も昔も首位独走状態です。Cレベルの人が、こういう日陰の仕事をやり続けていることが、コミュニティのモチベーション維持につながっているんじゃないかと前々からおもってます。"Lead by Example"の鏡だと思います。
Fluentdコアのリーダーは@frsyukiですが、ドキュメント側のリーダーは@kzk_moverだと思ってます。
さすがリヴァイ兵長に激似なだけありますね(関係ない)。
最後に
「Fluentdのドキュメント手伝ってよ」と、トレジャーデータの創業チームに声をかけてもらわなかったら、OSSの事を良く知ることも関わることも、日本のウェブエンジニア界隈の人たちと仲良くなることも、一生無かったでしょう。この場を借りて@yoshikawahiro、@kzk_mover、@frsyukiの3人に感謝の気持ちを述べたいと思います。
アメリカ在住であまり日本に行く事は無いのですが、2月に東京に中期滞在するので、是非一緒にうまいもの食べましょう。@hkmurakamiをつついてください。
[1] え?お前がやれって?gkbr