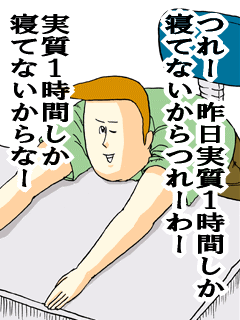
Source: 惚れさせ155
日米共通の問題として、「ワーカホリック信仰」がある。働くことは良い事で、休むことは働く事に比べると良くないという考えだ。そのせいで休むことに罪悪感を感じることは、どちらの国でもあることで、大企業もベンチャーも例外ではない。
AmicusというYCombinatorに出資を受けているスタートアップの創業者であるSeth Bannonはこう呼びかけている。
Professional runners take long breaks between marathons. They make no excuses for this, and no one judges them for it, because everyone knows that rest and recuperation is an essential part of being a pro athlete. The same is true for entrepreneurs (and everyone, really). Preventing burnout is part of your job. Staying well rested is part of your job. Sleep and exercise help, but occasional extended breaks are essential too, and their benefits on creativity, productivity, and happiness are well documented.
It’s time we stopped making excuses for rest and relaxation. Doing so is not only bad for you, but sends the wrong message to the rest of your team. So next time you’re planning a vacation, announce it with pride.
プロのランナーは、マラソンとマラソンの間に長い休暇を取る。言い訳などしないし、他の人も変に思ったりしない。プロのアスリート達にとって、休養は必要不可欠なものだと皆知っているからだ。これは起業家にとっても(そして誰にとっても)真理だ。疲労で燃え尽きるのを防ぐのも私たちの仕事の内だ。よく休むことも私たちの仕事の内だ。睡眠や運動は助けになるが、たまに長期休暇を取る事もまた必要だ。長期休暇が創造性、生産性、そして幸福度に与える恩恵はすでによく研究されている。
私たちはもう、休み、リラックスすることに対して、言い訳をすることをやめるべきだ。言い訳をするのは自分に悪影響を及ぼすだけでなく、チーム全員に間違ったメッセージを送ることになる。だから次に休暇を取るときは、誇りを持って宣言して欲しい。
Seth Bannon: Vacations are for the Weak
僕はしばらく働きません!(ドヤァ)